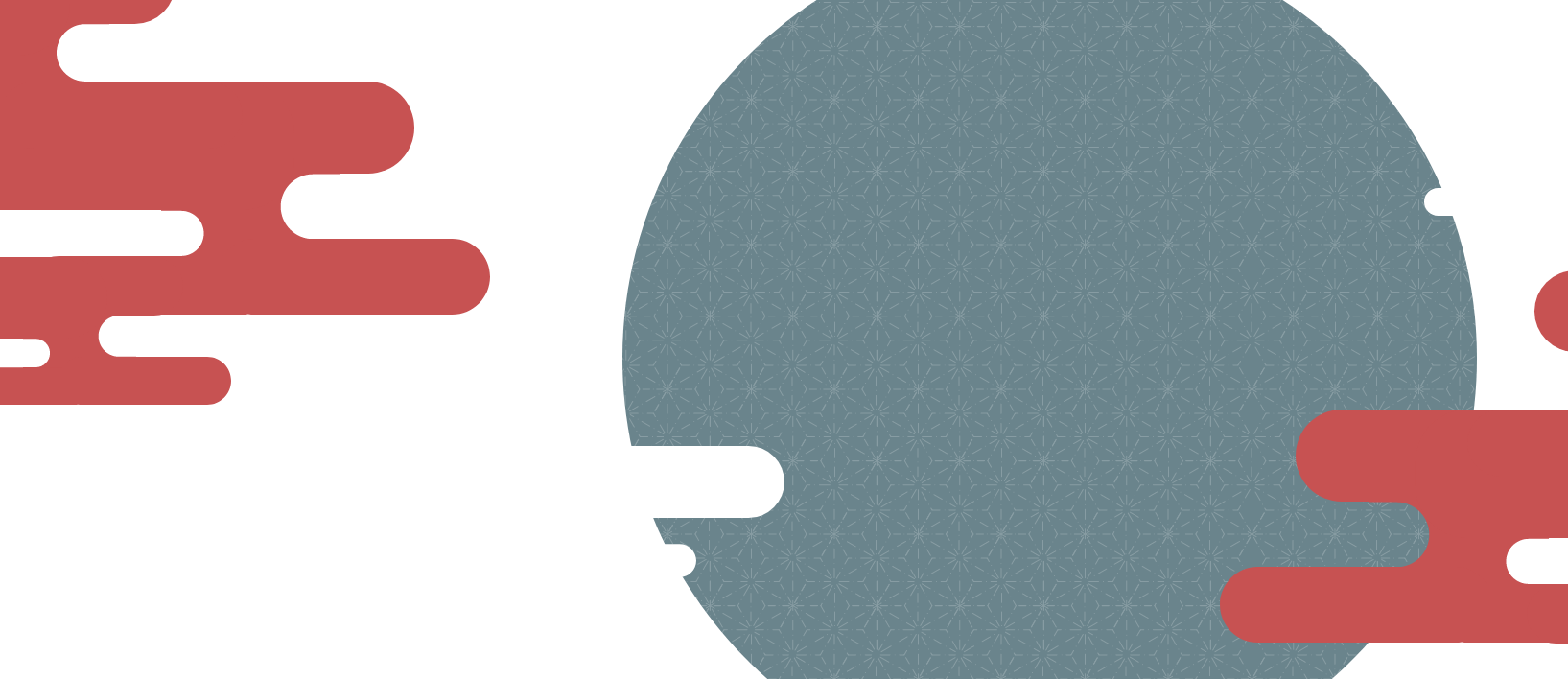アマゾニア(Amazonia)
ヤン・ヴァン・デル・ロースト(Jan Van der Roost)作曲
さて大曲アマゾニアの紹介です。日本の吹奏楽界では知らない人はいないであろうヤン・ヴァン・デル・ロースト先生の1990年の作品です。(ヤン・ヴァンデルローストの紹介はこちら→フラッシングウィンズ、その他曲はマーキュリー)
この曲は5つの楽章で構成された作品です。題名から分かるようにアマゾンにまつわる5つのテーマが各楽章で表現されており、全ての楽章は途切れること無く演奏される演奏時間12~14分の大曲です。
詳しい曲の説明は検索すれば出てくるのでそちらを見ていただくとして超簡単に説明すると
「第1楽章:ラグーナ・デル・シンベ」はヒーリング効果があると信じられている湖の名前でその湖がある神秘的な村の情景がイメージされている。
「第2楽章:アグアルナ」はペルー北部の先住民族の名前で儀式的な踊りが表現されている。
「第3楽章:メカロン」はアマゾン地帯の先住民であるインディアンの言葉で象徴・魂という意味をもつ単語で、インディアン文化のすばらしさを表現。
「第4楽章:ケートゥアヘ」はブラジルのクラホ族が行う成人の儀式の名称。
「第5楽章:パウリノ・ファイアカン」はブラジルのダム建設案に抗議しインディアン部族のために熱帯雨林を守ったの酋長の名前で、英雄ファイアカンの凱旋の様子が表現されている。 という感じです。
曲はファゴットの(高校ではバリトンサックスでしたが)低音の響きとパーカッションによる神秘的で静かな幕開けです(第一楽章)。金管の力強いメロディのあとにクラリネットが入ってきます。チャイムと金管と木管の複雑な絡みとシロフォンの活躍!トライアングルも重要そう。
テンポアップからは金管のかっこいいメロディです(第二楽章)。タイミング間違えると恥ずかしいところを過ぎると木管のメロディ。このあたりは指揮も奏者も難しいところだと思います。そのあとのメロディは一番印象に残っているかなぁ。
激しいところを過ぎると、ユーフォとホルンの美しいメロディ(第三楽章)。ここ大好きです。本当にいいメロディとハーモニィ。そのあとはまた妖艶な響きのフルートとクラリネット。ソロ的な各楽器の見せ場もあって飽きさせませんね。
8分すぎたあたりから再び何かが始まるような不思議な音楽へと(第四楽章)。ティンパニがすごい。なんか全部が激しいところを過ぎるとソプラノサックス(高校ではクラリネットでやった)のソロがあります。そしてクライマックスへ!まだまだ気の抜けないリズムが続く…。最後は急に明るいクラリネットのメロディがやってきて(第五楽章)フィニッシュです。この最後のメロディを聞くと当時を思い出して懐かしくなります。私の青春時代ですね。
聞いたら分かると思いますがまぁ難しい曲です。曲のイメージを掴むのが難しいのも然ることながら、入るタイミングとかそういうのがいちいち難しい…。曲のいたるところにトラップしかけられてる的な?!最後まで気を抜けません。何回合奏しても正しいタイミングで入れないところありみたいな。乗り切れないというかなんというか。
奏者は大変なんですが聞いているとさまざまなメロディとリズムがあってまったく飽きさせない曲ですよね。私が人生で初めて出会った大曲です。高校1年の定期演奏会でやりました。当時の3年生は各パートに上手な部員が居たのでなんとか曲にはなっていたと思います。指揮者の先輩も才能のある人でした。
とにかく記憶に残っているのはバリサクの先輩の音が大好きだったのと、クラリネットの先輩のソロの緊張感と、指揮者の先輩のみんなを引っ張っていく上手さと、パーカッションのスラップスティック(長い下駄みたいな楽器)の入ってくるタイミングよく出来るなぁっていうこと 笑。
当時の私は部活にあまり熱心ではなかったので、なんだよこの曲難しくてわけわかんねぇ~って思ってましたが、いま思えばこの曲をもう一度どこかで演奏する機会はそうそうないのでもっと一生懸命曲を分かろうとすればよかったなぁという後悔の念。
この曲をまた演奏する日が来るだろうか…もしあったなら高校時代を懐かしみながら楽しく演奏できる気がします。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/167a9f87.300fc378.167a9f88.aa9fd905/?me_id=1198247&item_id=10007838&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbandpower%2Fcabinet%2Ftoset-%2Ftoset-0708.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbandpower%2Fcabinet%2Ftoset-%2Ftoset-0708.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
【お取り寄せします 約10日間】アマゾニア 作曲:ヤン・ヴァンデルロースト Am…
|